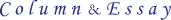- 2021.01.02:第三十四話「オムライス」
- 2020.12.25:第三十三話「トンテキ」
- 2020.12.16:第三十二話「アメリカンドッグ」
- 2020.12.14:第三十一話「タンメン」
- 2016.12.06:続・深夜食堂
- 2015.03.11:映画「深夜食堂」
- 2015.02.11:第三十話「年越しそば」
- 2015.01.26:第二十九話「レバにらとにらレバ」
- 2014.12.16:第二十八話「きんぴらごぼう」
- 2014.12.09:第二十七話「しじみ汁」
サブ・コンテンツ
- 2026.03.01:[YouTube] ダーリン 練習段階
- 2026.02.23:[通勤の音楽] 馬鹿丸出し軍団
- 2026.02.23:[YouTube] about yt 練習段階
- 2026.02.23:[YouTube] 僕の友達は平和が大好きだ 練習段階
- 2025.08.18:[Radio] 平和は、この曲であろう。31日目 蒼い星くず
第二十二話「豚バラトマト巻き」
文・鎌田浩宮
漫画編集者の宇野(ダンカン)が橋本ワタル(石田法嗣)を連れて店にやってきた。橋本は、宇野の担当する漫画雑誌の新人賞をとった漫画家の卵だ。宇野はマスター(小林薫)の豚バラトマト巻きを橋本にふるまう。
半年後、店で出会ったのりこ(椎名琴音)と同棲しながら、漫画を描き続けている橋本だったが、受賞後も連載デビューすることができず、まるでヒモのような生活を送っていた。宇野が豚バラトマト巻きを食べさせた新人は芽が出ないという因縁はほんとうなのか。橋本は徐々に自分を追いつめていく。
(公式サイトより抜粋)
骨肉と、
同じもの。
2話続けて、表現者、芸術家の話とは思わなかったなあ。
僕にとっては、とっても身近な話、というよりかは、自分自身の話、しかも、自分の立派な話なんかじゃあなくって、自分の至らなさをブラウン管で観るようなもの。
僕も、10代の頃から続けていた映画と音楽の制作は、30歳になっても芽が出なかったら、辞めようと思ってた。
これ以上周りに、迷惑もかけられない。
30歳が、成人式のように感じたなあ。
なんでこの世の中には、好きな仕事で飯が食える人が多いのに、なんで俺はなれないんだろう?
子供の頃から頑張ってきた夢を、諦めなきゃならないつらさ。
自分は才能がなかったんだな、凡人だったんだな。
自分以外の皆が知っていて、自分だけが知らなかったこと。
僕なんか馬鹿だったからね、井の中の蛙だったからね、自分は絶対なれると思って疑わないんだよ。
子供の頃からちやほやされて、周囲の友人の中では抜きんでているように見えて。
そんな自分とお別れするのには、時間がかかった。
でも、お別れしてからが、楽しかった。
で、結局3年だけ延長して、33歳でサラリーマンになるんだけれど、それから先の方が、いい作品が創れるようになっちゃったんだ。
それに、創ることが、楽しく思えるようになった。
だからね、このドラマに出てくる、手塚治己さんと同じ。
彼女に、
作品、
読ませたかい?
前作でも書いたけれど、僕は不特定多数の人に対して、ものを創らない。
だって、武道館で1万人を集めるのなんて、無理だもん。
身近でいつも僕を助けてくれる人や、寄り添ってくれる人へ、そんな1人1人に、喜んでもらえればいい。
でも、それで食べていくんだ、それを職業にするんだという時は、それを見失いがちだ。
自分のマンガが載っている週刊誌は10万部も売れていて、となれば、それも無理はない。
もう2度と出逢えないような恋人へも邪険にし、様々な大事なものを駄目にしていく。
そこで失ったものは2度と取り戻せないかも知れないけれど、でも大丈夫。
北野武の映画で唯一いいと思った映画でも、こう言っている。
まだ始まってもいない、と。
マンガを取ったら、
何も、
残らない。
残っているじゃないかよ。
僕の周囲で、その道で食べることができて、様々な作品を世に出している人もいる。
でもその作品が、全く僕の胸を打たないことも多い。
ひがみで言っているんじゃない。
不特定多数に対してものを創ると、こんなにその人の良かった部分が削られてしまうんだ。
アマチュアの時は、あんなに鋭角な作品を創っていたのになあ。
まずは、あの時身近にいた僕らを、喜ばせてほしいのになあ。
あの時身近にいた僕らを、今でも大事に思ってほしいのになあ。
スポンサーの、クライアントの、プロデューサーの、視聴率の、集客数の、会社のお偉方の、せいにするのは簡単。
…というのは僕の思い上がりで、「成人式を迎える」ということは、そういうことなんだろう。
そして、レス・ポールが、重たすぎたんだろう。
僕の映画や音楽は、多くの人の前にさらされないものがほとんどだけれど、でも、その作品で泣いてくれる人がいる。
ひょっとしたら僕は、もちろん手塚治己さんは、幸福な道を見つけられたんじゃないかなあ。
治己さんは、最高の伴侶を、最高の読者を、最高の創作仲間を、いっぺんに見つけてしまったんだから。
こんな僕でも、いるんですよ(伴侶以外は)。
僕は、サラリーマンになったら、きっぱり創作から足を洗う気概でいた。
でも、朝から夜遅くまで興味のない仕事をさせられる会社も、苦にならなかった。
そしていつの間にか、空いている時間に、再び映画や音楽の制作を始めていた。
僕は何のとりえもない人間だけど、この創作ってやつは、最後の最後まで僕にまとわりついて、僕と分離できなかった。
僕にとって創作が切っても切れないものになってしまったのを痛感したのは、息子同然に育てていた愛猫を震災以後に亡くした時だった。
僕は息子を失い、何もできず、毎日のように泣くだけで、外にも出なかった。
でも、それから少しして、僕は、彼があの世で聴いてくれさえすればいいと思い、曲を創り始めた。
1カ月ほど、朝から晩までキーボードに向かった。
完成してしばらくして、僕にとって創作がこんなにも大事なものだったのか、切り離せないものなのかと思い、愕然とした。
今回の主人公が、鏡に自画像の断片を描くカットがある。
ゴッホのように耳をそぎ落とす振りをすれば、真の芸術家なのか?
マスターが、優しく話しかけてくれる。
「逆じゃないのかな。全部なくしたつもりで、最後まで残っちまったものが、マンガだったんじゃないのかい?」
Column&Essay