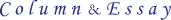- 2020.02.13:好きな映画を仕事にして 第2回
- 2020.01.07:好きな映画を仕事にして 第1回
- 2017.11.28:パターソン
- 2017.03.16:わたしは、ダニエル・ブレイク
- 2017.03.04:沈黙
- 2017.02.25:この世界の片隅に
- 2016.07.27:団地
- 2016.04.18:恋人たち
- 2016.04.15:コミュニティテレビこもろにて放映
- 2016.04.13:渥美清こもろ寅さん会館にて「男はつらいよ・翔んでる寅次郎」35㎜フィルム上映
サブ・コンテンツ
- 2026.03.01:[YouTube] ダーリン 練習段階
- 2026.02.23:[通勤の音楽] 馬鹿丸出し軍団
- 2026.02.23:[YouTube] about yt 練習段階
- 2026.02.23:[YouTube] 僕の友達は平和が大好きだ 練習段階
- 2025.08.18:[Radio] 平和は、この曲であろう。31日目 蒼い星くず
二番館へ走れ:第5回 『告白』
『嫌われ松子の生涯』に驚愕した中島哲也の新作、今度も驚愕。『嫌われ松子』ほどに分かりやすい仕掛けに満ちてはいないが、相変わらず画面は細かく加工されている。クラス担任による「このクラスの中に私の子どもを殺した犯人がいます」という告白から始まる物語はとんでもない展開で観客を思春期の地獄と復讐の闇へと突き飛ばす。
中学生たちも、空回り教師も母親も俳優たちが実にいい。が、なんと言ってもクラス担任の松たか子が圧巻である。最後の台詞のすざまじさよ!
直接人体に刃物が刺さるカットはほとんどないものの映画は血だらけ。それどころか発端の中学生による幼児殺し(あらためて文字にするとなんと救いのない行為であることか。しかもその動機たるや。)は幼児をプールに投げ込むことで完了するのだが、どう見てもその年頃の子どもを本当に投げているとしか見えず思わず「いいのか!」と止めたくなった。通常国産のテレビにしろ映画にしろ人が落下するに類する場面は人形を使っていて、たいていの場合バレバレなので客は白けながらその場面を見ているものだ。中には本当に人が落ちているとしか見えなものもあって、しかもご丁寧に人体が地面に着地するまでを一カットで見せたりして、その時当然にも観客は驚く。あるいは見てはいけないようなものを見たような気になる。しかも今回の場合被害者はタブーである幼児だ。その衝撃は二重である。この映画の本気さが分かろうというものだ。
が、僕が久しぶりに映画館で震え上がったのはこの場面ではない。一度目は出会いの中での希望を感じさせる言葉として、しかし二度目はバラバラにされた死体の入った冷蔵庫を前に悪意に満ちた言葉として繰り返される「缶ジュース、飲む?」でもない。少年Aの母が家から出て行く場面だった。それは子が親に捨てられる場面であり、哀れを誘う場面であるのかもしれないが、少年Aはそこで母親に決定的に呪縛されてしまうのだ。それは事件の遠因、結末へと連なる悲劇のささやかな始まりである。しかしそこに感じるのは恐怖よりむしろ少年Aの痛みである。恐怖ではなく痛みで震え上がった映画は今のところこの一本きりだ。(身体的な痛みの描写で震え上がった映画なら、例えば三池崇史の『ぼっけぇ きょうてぇ』がある。)
ムービックスつくばで平日夜に見た。二十人ほどの客。この劇場はエンドクレジットが始まると照明を点けてしまう。松竹の方針なのか?やめていただきたい。近場での上映はこの日が最後だったので、残念だがまだ二度目は見ていない。
様々な思いは見事に空回りし、惨たらしい結末に至る。登場人物は誰一人救われない。観終って、あの頃誰も殺さなくてよかったと思った。
蛇足。
クラス担任は一言も「死刑にしたい」とは口にしていない点に注目したい。死刑存置の論拠に「被害者・遺族感情を考えろ」というものがある。それを考えた結果、劇中のクラスではいじめが発生し、しかも途中からゲームになった。遺族感情を口実に自分の正義を証明し日頃の鬱憤を晴らそうとしていないかはよく考えたほうがいい。クラス担任は「殺したい」とは言っても死刑は望んではいなかった。彼女が望んだのは自身による処罰であり、国が代行しての殺人ではない。この二つは(おそらくは意図的に)混同されているが全く別のものだ。遺族が加害者を許しても死刑は行われる。つまりそもそも死刑は遺族感情に配慮されてなされるものではない。この映画の中でのゲームには眉をひそめるが、僕たちは現実の中で何に加担しているのか?
Column&Essay