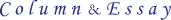- 2020.02.13:好きな映画を仕事にして 第2回
- 2020.01.07:好きな映画を仕事にして 第1回
- 2017.11.28:パターソン
- 2017.03.16:わたしは、ダニエル・ブレイク
- 2017.03.04:沈黙
- 2017.02.25:この世界の片隅に
- 2016.07.27:団地
- 2016.04.18:恋人たち
- 2016.04.15:コミュニティテレビこもろにて放映
- 2016.04.13:渥美清こもろ寅さん会館にて「男はつらいよ・翔んでる寅次郎」35㎜フィルム上映
サブ・コンテンツ
- 2023.03.26:[Radio] walkin’ to the beat everlasting⑦
- 2023.03.04:[Radio] walkin’ to the beat everlasting⑥
- 2023.02.26:[Radio] walkin’ to the beat everlasting⑤
- 2023.02.25:[Radio] walkin’ to the beat everlasting④
- 2023.02.19:[Radio] walkin’ to the beat everlasting③
エプスタ編集長による『東京家族』
写真/文・鎌田浩宮
これからこの映画を観る人のために、
極力あらすじに関することは書かないで行きますね。
「東京物語」
から
60年後
の、
東京。
早く観たくって、去年から、うずうずしてた。
僕が山田洋次作品のファンだということは、このエプスタでもこちらなどで、たっぷし書きました。
2月1日の映画の日に、1番スクリーンのデカい映画館で観たいと銀座に行き、上映時間の1時間半も前に到着し、席を確保した。
時間がだいぶ空くので、歩いて10分もかからない、1967年オープンの歴史ある銀座シネパトスへ。
ここは都会には珍しい名画座で、この時は、寅さんを中心とした山田洋次特集を2ヶ月近く上映していた。
ああ、こっちも観たいなあ。
今や珍しくなってしまったフィルム上映のこのコヤも、3月末で閉館しちゃうのだ。
なんでこの国は、再開発の名の下に、古いものを愛でることを、やめてしまったんだろう。
古いものには、温もりが、ある。
心が、落ち着く。
ピカピカなものばかりは、疲れる。
そして、有楽町マリオンに戻る。
相変わらずこの手の映画のお客さんは年配の人が多く、しかも映画の日だというのに、客の入りはいまいちだった。
しかし2時間26分という長尺で、途中で席を立つ観客も少し見受けられたのに、僕はちっとも長く感じず、年輩の客に混じって涙をすすった。
既に小津監督の「東京物語」を、何度も観たことさえあるのに、です。
さて。
映画が始まって、嫌な予感が早速当たってしまった。
フィルムにこだわり続ける山田監督は、この作品ももちろんフィルムで撮影した。
だけれどものすんごく残念だったのは、それを上映する映画館は、既にフィルムでは上映できず、デジタル上映ゆえに、若干だけど、画質が悪いんである。
あたかも、テレシネを観てるかのように。
博
と、
さくら
が、
出ている。
クランクインが大幅に遅れたことによるキャストの大幅な変更も、かえって良かったんじゃないかというほど、意外に役者がよかった。
山田組の常連の出演者が少ないので、不安だったのだ。
当初、父の役は橋爪功ではなく、菅原文太であり、長女役は中島朋子ではなく、室井滋だった。
菅原文太の方が、広島生まれの頑固親父の雰囲気は出るが、橋爪功の方が、背中を丸めてとぼとぼと東京を彷徨う笠智衆の味わいを出せたはずだ。
そして室井滋だと、杉村春子以上に、室井自身へ元々備わっている嫌味が出てしまう。
清純派の中島朋子が、嫌味を両親にぶつける意外さがとてもよかった。
ただ、母の役は吉行和子もよかったけれど、病気で今回降板した市原悦子の演技も観てみたかったなあ。
戦争未亡人だった原節子の役を、フリーターだが懸命に現代を生きている次男(妻夫木聡)とその恋人(蒼井優)に設定を変更したのも成功していた。
次男は、つまり「男はつらいよ」でいうところの、博なんである。
博は、エリート一家の中ではできそこないで、高卒で印刷屋の職工だ。
しかし人間に対する眼差しは人の何倍も真摯で、人を愛する気持ちもまっすぐだ。
だから博の母が亡くなった時の家族が集まったシーンで、おざなりの言葉で「母は幸せだった」と言い放つ兄に、泣きながら抗うんである。
それと類似したシーンが、吉行演ずる母の葬儀の後で観ることができ、山田洋次自身の人間に対する眼差しが変わっていないことを感じられて、嬉しいんである。
となると蒼井優は、さくらになる。
演技の清楚な清々しさも、倍賞千恵子に通ずる。
ただ、蒼井演ずる紀子は、さくらとも、原節子の紀子とも、少しだけ違う。
橋爪演ずる父の無口さを、つい愚痴るシーンがあるのだ。
驚いた。
さくらも、原の紀子も、決して愚痴らなかったから。
あの差異はなんなのだろうと、監督の意図を未だに考える。
「東京物語」と、大筋は変わらない。
だからストーリーは知っているのに、泣いた。
長尺も、気にならなかった。
だが、家に帰って原稿を書こうとすると、筆が進まない。
なんなのだろう、この心持ちは?
何日も何日も、日ばかりがすぎちまった。
山田監督は、映画のパンフレットに、こう記している。
「2011年4月1日
クランクインを目指していたこの映画は、
準備の段階で3・11の東日本大震災、
それに引き続き福島原発メルトダウンという
歴史的な事件に遭遇し、
製作を延期することにしました。
3・11以降の東京を、
或はこの国を描くためには、
どうしてもそれが必要だと感じたのです。
あれから11ヵ月。
新たに書き直した脚本で
クランクインを迎えます。
これは、2012年5月の東京の物語です。
長く続いた不況に重ねて大きな災害を経験し、
新たな活路も見いだせないまま苦悩する
今日の日本の観客が、
大きな共感の笑いと涙で迎えてくれるような
作品にしたいと、心から願いつつ
撮影を開始したいと思います。」
失われた
代弁。
だけど、この映画には、原発事故にまつわるエピソードはもちろん、原発という言葉さえ、結局1度も出てこなかった。
仕方が、ないんだろう。
スポンサーが、逃げてしまう。
まして、松竹は大企業だ。
しかしそれを差し引いても、地震や津波に関するエピソードやメッセ―ジが少なすぎる。
被災地に住む山田映画のファンは、
「ああ、自分たちの苦しみや悲しみを代弁してくれた」
と納得してくれただろうか?
それに、山田監督の知名度は高い。
監督が一言反原発を訴えるだけで、どれだけの社会への影響力があるだろうか。
僕らに勇気を与えてくれるだろうか。
サブテーマ
の
豊かさ
が。
山田監督は、どんなテーマの映画にも、その時の社会にある問題を取り入れてきた。
前作「おとうと」は姉弟愛がテーマの映画だけど、家族のない野宿者や無所得者(笑福亭鶴瓶)の終末=死の保護施設をしっかりと描いていた。
その前の作品「母べえ」も、戦時中に思想犯として獄死した夫の元へ、その数十年も後にようやく逝こうとする臨終の妻(吉永小百合)に
「やっとお父さんと会えるのね」
と慰める娘に対して
「生きているお父さんに会えなければ全く意味がない」
と、怒りの言葉を残して息絶える。
こうした社会への眼差しはコメディーにさえも描かれている。
「男はつらいよ 寅次郎サラダ記念日」では、田舎の孤独な老人の終末医療を描いている。
最終作「男はつらいよ 寅次郎紅の花」のラストシーンでは、阪神淡路大震災後の神戸市長田区でロケを敢行し、そこで復興を祝い歌い踊るのは日本人ではなく、チマ・チョゴリを着た在日コリアンの人々だった。
というように、本筋のテーマとは別に、様々なサブテーマを盛り込むことによって、映画全体が豊かなものになっていたんだと思う。
常に弱き人、苦しみの中にいる人、多数ではない人、悲しんでいる人へ、こんなに素晴らしい眼差しを忘れなかった名匠も、原発というタブーはおろか、地震や津波にも踏み込めなかったのが、長年のファンとしては残念でならないんです。
おそらく、「東京家族」を観た人の中には、
「震災に関することは、このくらいの盛り込み加減で、丁度いいんだ。あまりに盛り込みすぎると、小津安二郎の描いた本筋から離れてしまう」
という人も、いると思う。
僕が言いたいのは、その量ではないのだ。
質なのだ。
被災者にとって、いや、僕らこの国に住む人にとって、溜飲の下がる代弁であったか。
僕らの抱えているこの社会の問題を、家族の絆の再生という本筋のテーマに、押し付けてしまっているように見えてしまう。
敬愛している監督の批判を書くのは、嫌なもんです。
2013.02.15Column&Essay