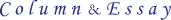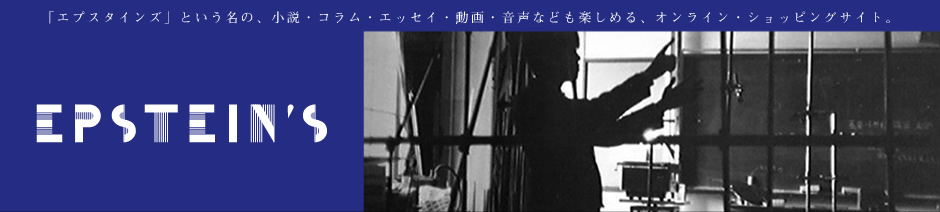- 2023.01.14:私の2022年映画ベスト21 鎌田浩宮編
- 2022.01.09:私の2021年日本映画ベストテン 鎌田浩宮編
- 2022.01.06:私の2021年外国映画ベストテン 鎌田浩宮編
- 2021.02.11:私の2020年映画ベストテン 鎌田浩宮編
- 2021.01.24:私の2020年文化映画ベストテン 鎌田浩宮編
- 2020.09.05:日本人の忘れもの ポレポレ千秋楽っ
- 2020.09.03:日本人の忘れもの つづきのつづきっ
- 2020.09.02:日本人の忘れもの つづきっ
- 2020.09.02:日本人の忘れもの
- 2020.04.02:コロナウイルスvs映画館 第4回
サブ・コンテンツ
- 2025.08.18:[Radio] 平和は、この曲であろう。31日目 蒼い星くず
- 2025.05.07:[CD] 阪急電鉄到着チャイムデモ集
- 2025.05.07:[CD] 阪急電鉄急行通過警告音デモテープ集
- 2025.05.07:[CD] 阪急電鉄梅田駅発車チャイム デモテープ集
- 2025.03.26:[CD] 柴田くんと本を出すのだ
私の2018年映画ベストテン 名無シー編 中編
新春恒例
名無シーによる
映画ベストテン。
連載第2回は
B級映画を含む
劇映画について。
では、どうぞ。
旧作のリバイバルでは日本初公開だったジャーマン・ニューシネマのライナー・ヴェルナー・ファスビンダーの二作品
「13回の新月のある年に」
「第三世代」
辺りは新作も超えられないような深みを持っていた。大きなスクリーンで各二回ずつ観た。カサヴェテス「こわれゆく女」に通じる空気感は、今日新しいリアリズムが海を越えて同じ空気を共有しようとしているのを髣髴とする。その他旧作にはグルジアのテンギズ・アブラゼの作品など、書ききれないけれど好いものが沢山あった。
旧年はB級以下のフィクションも沢山見た。その中で光ったもの。
パノス・コスマトス「マンディ 地獄のロード・ウォリアー」。
ニコラス・ケイジのパンツ一丁の独り芝居のシーンがキラキラしていた。ニコラス・ケイジは、ティム・ハンター「ダークサイド」でのマジックミラーの背後のしようも無い演技もなかなかで、しょうも無い人をやらせたらピカイチだ。今やB・C級の王座に据わっていると言っても過言ではない。
そして、ジュリア・デュクルノー「RAW~少女のめざめ~」。
ここでは一応B級として扱うけれど、あの洗練されたユーモアセンスは、超一級と言っていい。この人は本当に凄いと思った。メキシコの作家ホルヘ・イバルグエンゴイティアとか、星新一などのように、常人の及ばない確固とした達観があるように見えた。途中の姉の指が落ちるシーンの呆気なさや、クールな顔で落ちを言う話し方の様な、洒脱なラストの運びは、この後語る「リベンジ」同様、若い女性監督の擡頭を感じさせた。
その、コラリー・ファルジャ「REVENGE リベンジ」、
ぐるぐる追いかけっこシーンの緊迫感! 弱そうな女主人公がスタスタ走る様とか、割ったガラスをばら撒いたり、その他のシーンもみな馬鹿馬鹿しくも面白かった。画がどう見えるかについて洞察の深い若い女性達のセンスは侮れない。
探し物系の謎解きを秘めた映画も心に残った。
ハイファ・アル=マンスール「メアリーの総て」。
監督はサウジアラビアの女性だ。第三世界の女性に語ることが許されていることは、男社会によって厳に決められている。100年前のメアリー・パーシーを描いた映画に見えるが、本当はそうではないという見方も出来る。現代の彼女たちの話だと気付くと、見え方は変わる。何故他の話に仮託したのか。あれは彼女たちの潰されそうな叫びだろう。
同様に読み解くためのヒントが必要だったのは
白石和彌「止められるか、俺たちを」。
自殺した女学生の言葉という「解剖なんかだめ」と言うセリフ。この映画には、普通の観客が求める腑分けのような答えは何処にも用意されていない。その辺りは前にエプスタインズで対談した。
2018年は、映画好きが注目する監督達も新作を放った。
PTA「ファントム・スレッド」。
バロック絵画のような、あるいはコンテで塗りつぶした様な深い陰影。出だしで観客の目を釘付けにする、マジカルな程の、役者の動きと追うカメラによるワルツのステップの様なカメラワーク。今回は前二作と違って、超越的なシンボリズムを秘めたような人物ショットは無くなり、等身大の人の中のミステリーをあの深い影に塗り込めていた。
デヴィッド・ロバート・ミッチェル「アンダー・ザ・シルバーレイク」。
狭いハリウッドの奥に広大に広がるミステリーを巡る冒険譚。凄く面白かったけれど、前二作にあったデヴィッド・ロバート・ミッチェルらしい青い空気もまだ嗅いでいたいと言うファンは多いのではないかと思う。
ヨルゴス・ランティモス。役者に引き摺られたような新作は本当に残念だった。次に期待したい。
PTAの画作りについて語ったので、画作りが良かった二作品。
アンドレイ・ズビャギンツェフ「ラブレス」。
ロシアのツァイ・ミンリャンかというような、廃墟での捜索シーンを始め、森での捜索、リフォームされる子供部屋と、警察の聴取の時の教室それぞれの室内から窓外の雪景色へのパーン、扉の後から現れたぬらりひょんの様な強烈なインパクトの子供の顔、最初と最後の木に引っ掛かる凧、子供の視線の先にあった大空に上がりきれない凧。皆素晴らしかった。
そしてヤヌス・メッツ「ボルグ/マッケンロー 氷の男と炎の男」。
出だしのクレイコートの俯瞰、モナコのアパルトマンのベランダ上でのヨガのような身体性の大書から、ボルグとマッケンローのミルクレープの様な重なりが、幾何学的対称性を感じさせて、スクリーンを前にして、まるでチマブーエの絵か何かが飾ってある祭壇を前にしているような気分だった。
特徴で分けられないけれど、心に残った映画もある。ラテンビート映画祭で公開されたパラグアイ映画、
マルセロ・マルティネッシ「相続人」
は、主演のアナ・ブルンの捉え所の無い人物造形がぬきん出ていた。世界一物価が安いと言われる低成長国パラグアイの町の空気も良かった。
最終回、2018年のベスト3に続きます…。
Column&Essay