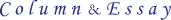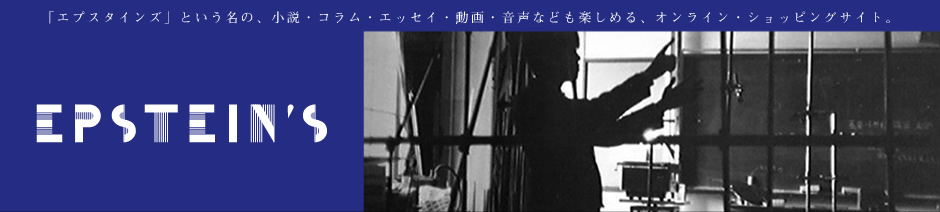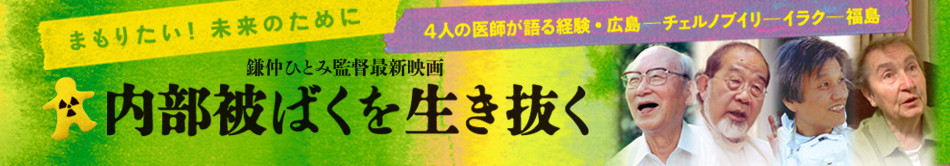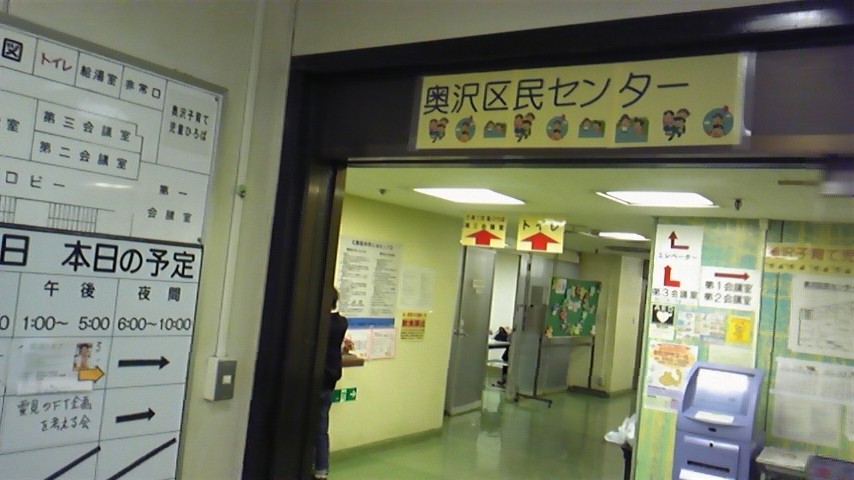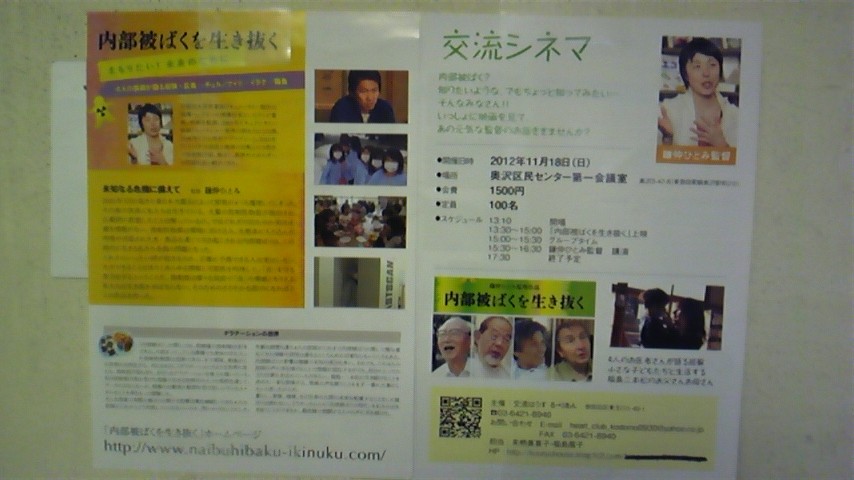- 2020.02.13:好きな映画を仕事にして 第2回
- 2020.01.07:好きな映画を仕事にして 第1回
- 2017.11.28:パターソン
- 2017.03.16:わたしは、ダニエル・ブレイク
- 2017.03.04:沈黙
- 2017.02.25:この世界の片隅に
- 2016.07.27:団地
- 2016.04.18:恋人たち
- 2016.04.15:コミュニティテレビこもろにて放映
- 2016.04.13:渥美清こもろ寅さん会館にて「男はつらいよ・翔んでる寅次郎」35㎜フィルム上映
サブ・コンテンツ
- 2025.08.18:[Radio] 平和は、この曲であろう。31日目 蒼い星くず
- 2025.05.07:[CD] 阪急電鉄到着チャイムデモ集
- 2025.05.07:[CD] 阪急電鉄急行通過警告音デモテープ集
- 2025.05.07:[CD] 阪急電鉄梅田駅発車チャイム デモテープ集
- 2025.03.26:[CD] 柴田くんと本を出すのだ
エプスタ編集長による番外編『内部被ばくを生き抜く』(前編)
文/写真・鎌田浩宮
ドキュメンタリー
映画
監督、
鎌仲
ひとみ
の
最新作。
東京で生活をしていると、八百屋さんやスーパーで手に入る野菜は、福島県に隣する茨城・栃木・群馬の野菜がほとんどで、放射能の心配をせずに済む西日本の物は、まず手に入らないんですよ。
あと、気になるのは、東京の水道水。
セシウムの値は低いが、他の放射性物質の値は調べていない。
内部被ばくは、微量でも体内に影響を及ぼすかも知れない。
311以降1年以上も、そうした恐怖から逃れられずに不安で仕方なくなるのを、日々ごまかしながら生きている訳で。
ネットでいくら調べても、内部被ばくに関しては、納得のいく答え、見つからなくって。
そんな時に、この映画、見つけまして。
この映画の鎌仲ひとみ監督は、元々NHKのドキュメンタリー番組にて、イラク戦争で米軍が使った劣化ウラン弾による被ばくを報道したのですが、テレビというメディアの限界を感じ、その後その題材を
「ヒバクシャ―世界の終りに」として映画化、その後は
「六ヶ所村ラプソディー」
「ミツバチの羽音と地球の回転」
と、日本の放射能問題を、次々とドキュメンタリー映画化してきたんですね。
そしてその最新作が、
「内部被ばくを生き抜く」なわけですが、これが面白い上映展開をしてまして。
こちらを見てもらうと分かる通り、日本各地で映画興行の「素人」の人々に主催してもらい、安価で全国の公民館などを廻ってるんですね。
具体的には、主催者が映画のDVDを3700円で購入し、上映会を開きますよと監督側に連絡し、監督側に来場者数×500円を支払う。
監督の講演も依頼したいなら、別途相談する。
(ちなみに、福島県内、および昨年の東日本大震災で被災された地域での上映会は、2013年3月まで、上映料を無料で受付しています)
こうして行われる上映会の入場料の設定は主催者に委ねられてます。
どこも大体800円くらいですね。
今回も、お母さんたちのグループが企画し、世田谷区立奥沢区民センターで上映。
しかも監督も来て、トークショウも見られて、1500円。
質問したいことは多々あったので、これは持って来いの催し。
2012年11月18日、自転車で、行ってきましたよ。
古い建物でしょう?
築40年以上、かも。
世田谷区の施設でも、珍しい古さ。
さてさて、お母さんたちというのは、僕のような役立たずな男よりも、
実行力、あるなあ!
今回は、自分の子供の父母会などのつながりが元になり、20人くらいの有志が集まり、口コミに手売りで、100枚もチケットをさばいちゃった。
で、監督自身も呼んじゃうんだから、すごいすごい。
パチパチ拍手ものです。
施設内には卓球場もあったりして、のどかな様子が、この催しとアシンメトリー。
胸、ちびっと、しめつけられます。
これが、今日の「映画館」の、入口。
中は満員のお客さんと、素人のお母さんたちのモギリ。
前売りだけで定員になっちゃってたんだけど、
「ネットで見つけて駆けつけたんです!」
と言ったら、特別に入れてもらえました。
お母さんたち、優しい!
そして僕の隣の席には偶然にも、反原発ラガマフィンラップで知られる、
あの、ランキン・タクシーが。
驚いたのなんの。
少し、お喋りしました。
監督のファンで、観に来たそうです。
チェルノブイリ事故の後、彼はRCサクセションの「ラブ・ミー・テンダー」「サマータイム・ブルーズ」とほぼ同時期の1989年に、反原発ソング
「誰にも見えない、匂いもない」を発表してます。
お客さんはやはり、お母さん方が多いけれど、おじさんもちらほら、若者もほんの少し。
お母さんの不慣れなれど微笑ましい司会と、皆の拍手で、上映開始。
映画は、体内被ばくの阻止に奮闘する4人の医師へのインタビューと、福島県二本松市で保育園を営む寺の副住職一家の生活を追って進みます。
凝った音楽やカット割りなどの演出を極力排し、資料性の多い構成です。
避難
できない。
理由
も
知らず
非難
される。
とにかく安全な食べ物をと、寺を運営しているネットワークを駆使し、県外から野菜などを段ボール箱で取り寄せ、保育園に通う親に無償で提供する副住職。
しかし、自分の子供の体内からセシウムが検出され、愕然とする副住職の妻。
やはり夫を置いて、県外へ疎開していればよかったのか。
園児の一母親へのインタビュー。
「私の家族だって、そんなに簡単に疎開できるなら、とっくにしている。様々な事情があってここから出られないのに、それも知らない人から非難されると辛くて…」
と泣いていました。
避難するにも、金がかかる。
避難後の仕事もなければ、収入がない、生活できない。
その他にも、沢山の事情が。
ましてや、副住職は、園児を見捨てて脱出することはできません。
数百万円をかけて、園の除染作業に取り掛かります。
ちなみに、一般家屋でまともな除染をしようとすれば500~1000万円かかるはずなのに、一軒あたり70万円しか支給されていないそうです。
がれき
問題
の、
ある
1つ
の
答え。
汚染された保育園の土をどこへ処分するか。
副住職は、自分の土地へ埋める決断をします。
「汚い物を他のどこかへ持って行くという発想は、原発をどこに建設するかという発想と同じ。だからよそに引き取ってはもらいません」
と、副住職。
このシーンを観て、がれき問題を思い出しました。
がれきを県外で焼却処分すべきかどうか、議論されています。
よそ者の僕が意見を押し付ける気は全くありませんが、汚染されたがれきを県外に持ち出したくないと考える人は、実は多いのではないでしょうか。
さあ、後編では、なかなか報道されていない様々な事実を、一挙に。
つづく・・・
<< エプスタ編集長による番外編『スケッチ・オブ・ミャーク』(後編) エプスタ編集長による番外編『内部被ばくを生き抜く』(後篇) >>
Column&Essay