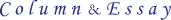- 2023.01.14:私の2022年映画ベスト21 鎌田浩宮編
- 2022.01.09:私の2021年日本映画ベストテン 鎌田浩宮編
- 2022.01.06:私の2021年外国映画ベストテン 鎌田浩宮編
- 2021.02.11:私の2020年映画ベストテン 鎌田浩宮編
- 2021.01.24:私の2020年文化映画ベストテン 鎌田浩宮編
- 2020.09.05:日本人の忘れもの ポレポレ千秋楽っ
- 2020.09.03:日本人の忘れもの つづきのつづきっ
- 2020.09.02:日本人の忘れもの つづきっ
- 2020.09.02:日本人の忘れもの
- 2020.04.02:コロナウイルスvs映画館 第4回
サブ・コンテンツ
- 2025.08.18:[Radio] 平和は、この曲であろう。31日目 蒼い星くず
- 2025.05.07:[CD] 阪急電鉄到着チャイムデモ集
- 2025.05.07:[CD] 阪急電鉄急行通過警告音デモテープ集
- 2025.05.07:[CD] 阪急電鉄梅田駅発車チャイム デモテープ集
- 2025.03.26:[CD] 柴田くんと本を出すのだ
港町
文・名無シー/鎌田浩宮
鎌田浩宮の友人にして、
年間に映画館で映画を
100本以上観ておる名無シー。
今回の「映画おとーり」で取り上げるのは、
想田和弘監督の新作ドキュメンタリー「港町」。
2人の対談を、お読みあれ。
美しく穏やかな内海。小さな海辺の町に漂う、孤独と優しさ。やがて失われてゆくかもしれない、豊かな土地の文化や共同体のかたち。そこで暮らす人々。静かに語られる彼らの言葉は、町そのもののモノローグにも、ある時代のエピローグにも聞こえる。そして、その瞬間は、不意に訪れる……。
監督は、イタリア、カナダ、中国などでレトロスペクティブが組まれるなど、国内外で高い評価を受ける映画作家・想田和弘。ベルリン国際映画祭2018への正式招待が早々と決まった本作は、作品を重ねるごとに進化を続ける「観察映画」の新境地であり、同時に、現代映画のひとつの到達点である。しかし、我々は、この映画体験の美しさと比類のなさとを語る言葉を未だもてずにいる。あなたは、どうか?
公式サイトより
鎌
昨日ようやく「港町」を観てきました。 観察映画と称していますが、作り手が介入しない芸術というものはあり得ません。その点を楽しみにしていました。
僕もドキュメンタリー映画を創った時に感じたんですが、被写体となる人達が身構えず普段通りにそこへ佇んでくれるのは、難しいものです。
原発事故の後、数多くのドキュメンタリーが創られました。作品の善しあしは別にして、多くの作品の被写体となる人々は、身構えてしまっているんですね。 何かを語らなくてはならないという焦りを、その人々から感じるんです。製作者の意図を汲んでしまっているんです。
「港町」は観察映画と称しているが、制作者と被写体のコミュニケーションが、とてもうまくいっていると思いました。だから、被写体があれだけ普段通りにたたずんでいる。ど田舎の人達が、他者を受け入れ信頼し、カメラに映っている。
名
写し手がそこにいるんですと言う当たり前をちゃんと撮ってますね。 しかも、映画を観る側をどこかに誘導する訳じゃないので、観る人によって、起きていることの解釈は分かれる。 クミさんの訴えは妄想か現実か、観客の皆、色々手探りするという。そこはフィルムでありつつ現実に近い感じですね。
鎌
そうそう。観察映画と言いながら、監督本人の声も結構入っています。ドキュメンタリーは、監督の声を排除する作品も多いですよね。
名
例えば最近の例だと、「ラッカは静かに虐殺されている」演出が入ってないとあり得ないシーン(仲間の死の報告を受けるシーンは、シームレスにカメラが幾つかの方向から撮っているリアルタイムっぽいシーケンスだけど、向かい合った位置のカメラが画角に入っていない)などが指摘されていました。
「港町」を観ると、もうそういう劇的な演出はいらないんじゃないかと思える気もしますね。
鎌
僕も映画を撮っていると、撮影時間は異なるのに、あたかも同時に複数のカメラで撮影したかのような編集は、よくやりますね。
名
演出的な編集技法が、「ラッカ~」では、ドキュメンタリーって何的なクリティシズムを誘発していたようです。精神的ショックの内面性は、演技で外化する必要はないと言う事かも知れません。
鎌
ドキュメンタリー作家にありがちなのは、マイケル・ムーア批判です。しかし、彼は現場において、被写体に過剰な演技を求め、引き出しているかというと、そうでもないのではと思います。むしろ、撮影を終えた後の編集に彼のこだわりがある。「ドキュメンタリーというものは、編集により客観性は消失するのだ」と警笛を鳴らしているのではないかと思うんです。
鎌
カット・編集で気になったのは… 例えばワイちゃんが魚から網をほどいているカット。長すぎるんです。どこでカットし次のシーンに移ろうと、作者の意図は露出するものなんです。どこでそのカットを切り、次のシーンに移るか。それはもう、観察の域を超えた行為なんです。
しかし、観察というコンセプトにこだわりすぎて、監督自身がどこでカットしたらいいか分からなくなっている、というか…。端的に言えば「うわあ、これが2時間続くのはきついなあ」でした。
鎌
いや、俺は嘘をついています。訂正します。 ムーアがチャールトン・ヘストンを過剰に怒らせた、普段よりも2割増しで怒らせたのであれば、それは演技をさせたということになります。 ただし、人というものはカメラを向けさえすれば、多少の演技をおのずからしてしまう生き物でもあります。 その点において「港町」の登場人物は、あまりにも自然でした。素晴らしいです。
カットについては…監督自身がそのタイミングを見失っているのではなく、彼なりの意図はあるのでしょう。でも、その意図は伝わらないというか、中途半端というか…。
名
カット、時間の伐り出し、確かに難しいですね。実はおれは、ワイちゃんの長回しは割と楽でした。昭和50年代のカメラで白黒写真を撮ったみたいなあの、アサカメ、ニッカメ上級者の投稿欄の写真みたいなあの時間は、オーケーでした。
プロデューサーで奥さんのカシワギさんが白黒で行こうと決めたそうで、それが正にハマったとおもいました。

マイケル・ムーアの演技っぽさは、政治家や財界人達の我々に対する演技にぶつけられた挑戦状で、ムーアさんはその闘いのドキュメンタリーを撮っているから他のドキュメンタリーとはまた違った地平で評価出来ると思っています。現実の中の悪しき演技を壊そうとしているのです。
鎌
なるほど、その通りですね。想田監督は今作をカラー作品で考えていたほど色にはこだわっていたようです。したがってモノクロの画質にも、質感がありました。極端なクローズアップもよかった。
唯一、ズームするとピントが合うまで時間がかかる…もっといいカメラ使えよ!とはすこ~しだけ思いましたが!
鎌
ムーアの分析も、なるほど!ドキュメンタリー映画というものは、あるがままを投影すればいい、起承転結はなくてもいいといったセオリーを曲解して、挑戦状でなくてもいいと思い込んでいる監督が多すぎます。原一男や森達也はもちろんのこと、「ソング・オブ・ラホール」といった作品さえ、挑戦状を表示する映画です。
<< 新作映画を撮っています 映画「マラソン・マン」公式HP >>
Column&Essay