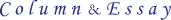- 2012.12.05:第九十九夜:「コスモスなどやさしく吹けば死ねないよ」
- 2012.11.14:第九十八夜:「わたしの想うアレやソレ」
- 2012.10.31:第九十七夜:「いきものアルバム最終回 <イヌ>」
- 2012.10.24:第九十六夜:「百夜通い」
- 2012.10.18:第九十五夜:「二度と辿り着けない場所」
- 2012.10.11:第九十四夜:「わたしの理想」
- 2012.10.03:第九十三夜:「ワカゲノイタリ」
- 2012.09.26:第九十二夜:「私は巨大になりたい」
- 2012.09.19:第九十一夜:「近頃のあたしゃ・・・」
- 2012.08.15:第九十夜 :「あなたは知らない世界」
サブ・コンテンツ
- 2025.08.18:[Radio] 平和は、この曲であろう。31日目 蒼い星くず
- 2025.05.07:[CD] 阪急電鉄到着チャイムデモ集
- 2025.05.07:[CD] 阪急電鉄急行通過警告音デモテープ集
- 2025.05.07:[CD] 阪急電鉄梅田駅発車チャイム デモテープ集
- 2025.03.26:[CD] 柴田くんと本を出すのだ
第四十二夜:「ソーダ色のペイジ」

今から二年ほど前に、中学の時の同窓会がありました。
会場にはひどく懐かしい顔、名を言われても思い出せない顔、
まだ付き合いのある女友達の顔。
それでも皆、年齢相応に経験と皺を重ねた顔つきになっていて、
それが嬉しかったり、過去を思い出して少しだけ寂しかったり。
話といえば、やはり入口は今の仕事の事や家族の事で、
それから中学時代を身体が思い出してくると、
恥ずかしい想い出や、笑い転げた日々が飛び出してくる。
そして、お酒が進めば必ず出てくる「初恋」の話。
当時友人だった女子達は、今や容姿が変化してしまった初恋の男子を
哀しそうに眺めながら、
「ハゲたねえ~」 「太ったよね~」 「残念にも程があるよ~」
偉そうに人の事をのたまう女子たちに
鏡で自分を見ていらっしゃいな!と突っ込みながらも、
私もまた会場内を探していました。
私の初恋の人を・・・。
結局、その同窓会には彼は来ませんでした。
幹事だった同級生曰く、彼は急遽来られなくなったのだそう。
だから、すっかり忘れておりました。
彼がやってきたのです。 当旅館に。
予約の電話は彼からでした。
全員に渡された現在地を知らせる名簿と、友人である幹事の話から、
私の旅館のことを知ったのだそうです。
声変わり前だった中学生時代よりも、彼の声は低くしゃがれていました。
続きは会った時にと、さほど電話では話はしませんでした。
彼は家族と来るとの事でした。
到着した彼と、彼の家族は見るからに穏やかな人間でした。
中学生の娘さんと、小学生の息子さん、そして彼と、奥様。
彼らは帰られるまで、絵に描いたような和やかな家族でした。
彼はあの頃の様子を残しながらも、強い大人になった様でした。
声を荒げるでもなく、どっしりと構えている彼。
奥様も終始優しく微笑んでいて。
そして健やかな子供達の心地よい声。
ものすごく、長い長い時間が経ったように感じました。
なんだか嬉しいような、寂しいような気分のまま、
その夜はゆっくりと更けていきました。
ウチのお土産売り場は出来るだけ遅くまでやるようにしていますが
その日は私が売り場を片付けようとしていた頃に、彼が一人で現われました。
アイスが食べたくなって、と恥ずかしそうに言いながら。
彼はソーダのアイスを買い、私にも勧めました。
私も当館を治める身ですから、今度は私がおごってあげました。
ロビーの喫茶フロアでアイスを食べながら、
私たちはたどたどしく語り合いました。
会話から、削られていくアイスから、私の中であの瞬間が甦りました。
彼はバスケット部で、私は陸上部でした。
運動神経抜群で、女子の人気も高かった彼。
でもぶっきらぼうで、女子なんかに興味がない、というそぶりも
一層人気に拍車をかけていたと思います。
彼には自転車のイメージがありました。
水色の美しいフォルムの自転車。
彼はいつもそれに乗って颯爽と帰っていく。
部活終わりの夕暮れ時、その姿を見る事は私へのなによりのご褒美でした。
今の私と違い、あの頃の私はひどい引っ込み思案でしたから
ただ彼と少しでも話すタイミング欲しさに、自転車通学をしたいだなんて
思っていたくらいでした。同じクラスだったのに。
そんななのに、一度だけ夜中に自転車で走っていた、
普段着の彼を見つけても、激しく動揺して声も掛けられなかった臆病者。
せいぜい私にできたのは、彼の自転車と同じ色の陸上用スニーカーを
買う事だけでした。
彼と二人きりで話せたのは、一度きりでした。
忘れもしない修学旅行の夜。
今の私と変わらず、方向音痴だった私は班の子たちとはぐれて
一人旅館に戻れずにいました。(実際はものすごく近かったのですが…)
クラスの皆が迷子の私を探しに回っていたらしく、
その時に彼が私を見つけてくれたのです。
私はといえば、もう道はわかんないんだから担任や誰かが
見つけてくれるまでいいやと、お土産を激しく物色しておりました。
「お前、何やってんだ?」
後ろから声を掛けられ、犯罪者でもないのに酷く驚いたのを覚えています。
そこには呆れたような、それでいてホッとしたような顔の彼がいました。
暑い日でした。
旅館までの帰り道、彼はアイスを食べたいと言い出し、
近くにあった駄菓子屋でアイスを買いました。 ソーダ味の。
彼は、私には何も聞かず、同じアイスを私にくれました。
無言のまま、私たちは歩き続けました。
私の前には水色のアイスを食べながら歩く彼。
彼の後ろ姿を見つめながら、削られて少なくなっていく私のアイス。
味なんて少しも分かりませんでした。
がっちりとした彼の背中。 汗ばんだ腕。 彼がアイスをかじる音。
私から言葉なんて出てこられるはずもなく、私はただ彼から
来るはずもない、ありえるはずもない何らかのアクションを、
じっと待っていたと思います。
知らない街を歩く彼と私。
不思議な気分でした。
世界に彼と私しかいないように思えました。
その時、彼は言いました。
「迷子になんてなるなよ。心配すんだろ…」
今思えば、少年のたどたどしさ漂う台詞でした。
私は一言「うん」と言い、その後何度か「ごめん」と言い、
最後に「ありがとう」と言ったと思います。
彼は「あやまりすぎ」と微笑みました。
ロビーで今のアイスを食べながら、私たちは話しました。
考えてみれば彼との接点は本当に少なく、大人になった今の生活は
ともかく、当時の事すらほとんど知らない事ばかりでした。
あの自転車の姿すら、彼にとっては違うものでした。
向上心に溢れていた彼はいつもバスケが上手くいかない事を
悩んでいたらしく、いつも帰りは怒りをぶちまけるように
自転車を漕いでいた事。
スポーツ万能だったのもそれは天性の才ではなく、彼のお兄さんが
運動も学問も凄まじい人間だったから、負けまいと小さい頃から
日々ハードに特訓していたからだった事。
少年時代の不満や憤りを、自転車で夜の街を疾走することで解消していた事。
私が迷子になった時の話も出ました。
「なんで私を見つけられたの?」と質問したら彼はあの頃を思い出したのか、
気恥ずかしさを零す表情で「どうしてだったかな?」と言いました。
私は「見つけてくれなかったら、今もまだあの店にいたかもよ?」と言うと、
彼は「どんだけだよ」と屈託なく笑いました。
部屋に戻る際、彼は不思議な事を言いました。
キミはあの頃とあんまり変わっていない、と。
私はあの日のように「ありがと」と言いました。
「だから少し話しづらい」とも彼は言い、「なによ、それ!」と
私も笑って返しました。
そしてこんな事を言って去っていきました。
「さっきの、あれ、ちょっと嘘。 夜、自転車で走ってた理由。
あれ、ホントは○○町をぐるぐる走り回ってた。そんだけ。おやすみ」
○○町は、当時私が住んでいた場所でした。
翌日、彼らは帰っていきました。
彼が今どんな人生を送っているかはわかりません。
でも、私の人生の、あるページには、彼との想い出があります。
人生のページはこれまで多くの事柄が追加されました。
もちろんこの邂逅も。
これからも様々に追加され続けるのでしょうが、
あの日のページだけは増えようがありません。
それは大人になればなるほど切ない事です。
現在の彼から聞かされた、あの日の真実のような何かから、
今更「あの時もしも・・・」を考えないわけではないですが、
少しだけ、あのページが、前にもまして愛おしくなりました。
そして、あのままでいいんだ、とも思いました。
あの日、私も、そして彼も、互いに自分の気持ちを探しながら、
歩いた知らない街の夜は
あのままでいいのです。
ただ、あの日の臆病者に言ってあげるなら、こんな言葉かな?
「この幸せ者!」
Column&Essay