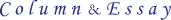- 2023.01.14:私の2022年映画ベスト21 鎌田浩宮編
- 2022.01.09:私の2021年日本映画ベストテン 鎌田浩宮編
- 2022.01.06:私の2021年外国映画ベストテン 鎌田浩宮編
- 2021.02.11:私の2020年映画ベストテン 鎌田浩宮編
- 2021.01.24:私の2020年文化映画ベストテン 鎌田浩宮編
- 2020.09.05:日本人の忘れもの ポレポレ千秋楽っ
- 2020.09.03:日本人の忘れもの つづきのつづきっ
- 2020.09.02:日本人の忘れもの つづきっ
- 2020.09.02:日本人の忘れもの
- 2020.04.02:コロナウイルスvs映画館 第4回
サブ・コンテンツ
- 2023.03.26:[Radio] walkin’ to the beat everlasting⑦
- 2023.03.04:[Radio] walkin’ to the beat everlasting⑥
- 2023.02.26:[Radio] walkin’ to the beat everlasting⑤
- 2023.02.25:[Radio] walkin’ to the beat everlasting④
- 2023.02.19:[Radio] walkin’ to the beat everlasting③
作品評:名無シー
鎌田と30年以上のつきあいがあり、
今やエプスタインズ専属映画評論家
とも言える、名無シーさん。
映画「マラソン・マン」について
評を寄せてくれました。
鎌田浩宮「マラソン・マン」 このドキュメンタリー映画は一般公開されていない。
監督や登場人物達とよしみのある数十人だけの上映会で上映され、内容も非常にプライベートな性格の強い映画だけれど、そのプライベートな事が寧ろ重要だった様にも思う。だから、この感想も、極めてプライベートな私信のようなものになるかも知れない。
集まった観客は、国の外交プロジェクトに関わるさる行政法人の職員やOB達、某大学でさる物故された教授と共に嘗て様々な社会問題に目を向けてきた自主ゼミのOBOG、某大学哲学科の出身者ら、人工知能工学の博士、生徒の自治がきわめて盛んだった某首都圏の高校の出身者、出版関係者ら、何者にもなっていない若者とこども各一名、映画関係者と大学の哲学の教師。
本来彼らは結婚式の席次のように互いを何者か認識して何等かの交流をすべきだったかも知れないが、その用意が無かったために、彼らは異常に強い好奇心で互いを注視し合った。
一組の初対面の男性と男性だけが、互いに自己紹介した上で、かなりプライベートな来歴と出自の歴史を掘合っていた。アンナチュラルに見えながらもナチュラルに。
自分の書いたアンケートを
朗読しろという観客が現れる
11月17日 午後7時40分、1時間半の上映が終わった後、観客がやや騒然とする事件が起きた。
上映後の質疑応答の中で、来場していた一人の中年男性が、自分で質問する代わりにアンケート用紙に書いた彼の否定的とも取れる感想を、監督自身にに読んで欲しい等と要求したのだった。
彼は一風変わった風体をしていることもあり、多くの観客は、相手にしてはいけないと、ヒヤヒヤしながら固唾を飲んだ。
多くの人が知らなかったが、彼はさる大学で教鞭を執る哲学の教師で、殆どの人が個人の体験として映画に触れる中で、そのプライベートな体験としてのこの上映会全体の中で、ある映画のシーンが持つ意味が他のシーンと性質が異なることを指摘しているようだったけれど、多くの観客は彼の言葉を封殺する空気の側に立った。
この事件は、理解者と無理解な大勢どちらの側から見ても、心に引っかかるとても大切な体験となった。多くの場合、違和感のある場所には何か大切な物が隠されている。
最初から横滑りしてしまったけれど、映画の話をしようとしていたのだった。
全国でロードショウ中の
とある映画との類似性
少し前にテアトルシネマで上映されて、今もドキュメンタリー系に強い中央線沿線のミニシアターでかかっているさる映画の製作の中心的関係者の方(有名人のプライバシーのツィートみたいになるので映画のタイトルは伏せる)も今回来場されていらして、だからというわけではないけれど、そのさる映画と今回観たこのドキュメンタリー・フィルムを何となく比べて考えた。
そのさる映画もこの映画も、共に強烈にプライベートなところに核があって、映画として次の時代に踏み出す足に逡巡がある。
商業的に出来てきたルーティンな製作作法に重きを置いて迷い無く作られているくだらない映画とは感じが違う。回収前提の資金を出す投資家への色目が無い。
プライベートとと言うことで思い付くことに、例えば私小説のようなものがある。今日の我々は、その実体験の断片を一つに繫ぐ接合のメカニズムであったり、あるいは実体験に盛られたり、または話のモデルとなった現実の中で実体験を誘導したりした古典的ストーリー性と言うものにどこかで飽きていて、ストーリー性に疑問を持たないことに違和感を見付けてしまったりすることがある。
そのストーリー性と言うものに、一見歪なものや前時代の整合性を壊すものであってもストーリーとしての 作られた纏まりが目に見えて意識されて、観客の前に何も考えず食えと膳が据えられる感じを看取る。
観客はまだ面白いストーリーを求めつつも、どこかではストーリーに飽きていて、いま自分達が欲しいものについて迷いがある。想田和弘氏の観察映画が注目されるのも、一つにはそう言うことがある。
件のさる映画も、一定のストーリー性は維持している様に見えながら、登場人物達のモデルとなった実在の諸氏それぞれの思いの齟齬からか、一つの誘導的なストーリーに纏めきれない散漫さの様なものがそこはかとなくあって、作中の「解剖なんかだめ」というヒントによって初めて、腑分けしてはいけないもの、関係者達が抱いた主人公や仲間達への お互い見えていたものは似ても似つかないそれぞれの愛が存在するらしいことがぼんやり炙り出しのように姿を現すという、真っ直ぐ観るだけでは済まない苦肉の策のような努力が潜んでいるのを見る作りになっていた。
しかも作中出だしの辺りで、「誰でも分かる映画」等と言うセリフを飛ばし、観客の前に高いハードルを並べてくる。
ひとつにまとめあげられた
物語など嫌だ
映画道場の様なその さる映画 には、勝手に一つに纏め上げられた物語は御免だという関係者達の幾度もの涙でにじんだような思いがあるように見えた。それ故にそんなハードルだらけの映画になった。
全員が、同じ誰かを、或いは仲間達お互いを、ハードルを壊して突き進みそうなほど深く自分のやり方で愛していたのだろう。
そのために さる映画 は映画自身に返る視線を映画の一部としてフィルムの外側に結わえ付けてあるような複雑なものに仕上がっていた。その事に気付くと嘗てあった出来事を知らない私も涙を誘われる気がした。
そして今回観たドキュメンタリー。
監督は一人の魅力深い親友をカメラで追い続けた。
映画の内容はその親友を知らない人に向けられたものと言う印象ではなかった。
パブリックドメインに移っていない映画等を勝手に引用している辺りも、一般公開を考えず、プライベートな仲間に見せようというつもりでいることを物語っていた。
彼を知っている人達が、彼の知らなかった面を知る事になるインタヴィウ、趣味かそれ以上に思い入れあるライフワークの様にも見えるマラソンに打ち込む様子、市井にまでにおってくる政治のまやかしへの怒りなどが詰め込まれている。
物語はない。監督と製作関係者はそのプライベートに見えるフィルムを誰に投げかけるべきか迷いがある様子だった。
登場人物・関係者へ配慮する一方
マラソンと関係ない映像の断続的挿入
プライベートとは言え、友人知人にも様々な人達がいる。どう見せるのか、どこまで見せるのか、その事が一般公開される映画と事なり、受け手一人一人、或いはその繫累への配慮もありながら、その方々の顔を思い出しながらだったと思しき編集は上映直前まで続いたと言う。
一方で、映画の中にありながら、ファンファーレとして映画の外にあるような、他のパートに対する撥水性の強い長い導入部が巻頭に設けられていた。
その導入部は、大衆に投げかける為の、言葉や映像等様々なレベルの説明や補足はほぼ割愛されていた。
飢餓に苦しむ人々の報道画像らしきものは、しかし、一人の誰かと言うよりは、記号的に第三世界の苦しみを現していて、映画の他のパートとはもはや別の映画のように趣を異にしていた。
くだんの哲学の先生がこの部分を不要だと評した。
恐らく、この映画の中にもう一つ異質なものとして挟まれた監督の思い入れのある心象的な景色のパートを映画全体の中で繫ぐなら、映画の一体性は飽くまでパーソナルな魂のところにあって、この導入部の混じり切らない撥水性が、障ると感じたのだと思う。
挿入された映像や音声は
主人公とまつわるものに
他ならない
この部分はファンファーレで、この後起きることとは別の、指を指すような喚起と捉えれば、この異質さは理解可能で、且つ記号的に現された国際情勢は、この映画の主人公の信念によって選ばれた職務を指差すものだった。
ただその理解を助ける補足はなく、逆に意味のくみ取りを阻害するかのようなキャプションが敢えて入れられていた。
この説明の排除は、監督の心象風景や、主人公と監督の東北の旅のシーンでも意図的と思えるほど徹底されていて、上映後に互いが確かめ合うことを予め前提されている様だった。
そこがこの映画の特徴に見え、くだんの映画製作関係者の方は、質疑応答の際、ずばりあるシーンに関して、これはどこですかと訊いていた。
アピチャートゥポン・ウィーラセタクーン的なオーバー気味な露出の緑の茂りのティルト映像などの心象風景に関しては、彼女はよく知っている場所だったため、質問はしなかった。
その事が、この映画の性格をよく現していた。映像や言葉の引用、提喩的な貼り付けも、どういう意図で引かれたかはわかりにくくなっていた。
本編の内容とは別に
仕込まれた「フック」
それこそが観客へのプレゼント
こう言う出来事、映画体験に慣れていない友人知人は面食らったはずだ。
ただ、この違和感は、人生のある晩に、仲間達と奇妙な映画を見た記憶として、思い出す人がいたなら、件のプロデューサー氏や哲学教師のように、質問や所感を監督本人に、私としては願わくば、観客同士やこの映画を観なかった人に対し、何年か前に奇妙な映画を見たんだけれど…… などと暗い飲み屋や宅飲みなどの際に語られるとすれば、この映画は望外の映画冥利をえるのだと思う。
あの、困惑の質疑応答は、その始まりとしてしっかりつとめを果たしたのだ。
先の さる映画の、物語を維持しようとしながらも物語から脱するところに本当の感情が隠されている作りや、このドキュメンタリー・フィルムのような物語以外の時間の流れの中で、謎のフックによって観客に土産を持ち帰らせる試み、こうしたことが明日に何かを届けるのだと思う。
観客の中にいた、あの若者とこどもは、何時かこの映画を見た晩のことを思い出すことがあるだろうか。
2018.11.23
<< 対談 深沢涼子・鎌田浩宮 対談 名無シー・鎌田浩宮 >>
Column&Essay